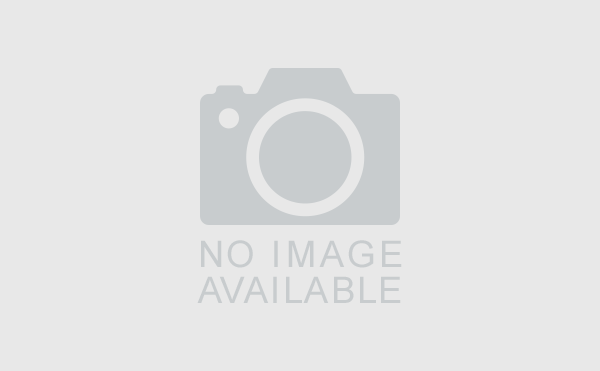中学校の成績のつけ方について
ここでは、昨今の沖縄県の中学校の成績のつけ方について書いていきます。(あくまで塾長の主観です。)
みなさんの中でも、ひと昔前に比べて中学校の成績のつけ方が変わってきていると思う方も少なくはないと思います。
全国的にも沖縄県については高校受験において内申点の比重がかなり高いです。なので中学校の成績のつけ方はかなり大事になってきます。
2020年に学習指導要領(中学校において授業・教科等のルール的なもの)の改訂がありました。これは10年に1回改訂があります。2020年の改訂後、通知表の評定の観点別評価が
①知識・理解 ②思考・判断・表現 ③主体的に学習に取り組む態度 の3つに変更になりました。ひと昔前までは5観点別評価になっていました。(塾長が学生時代)具体的にこれでどう変わるかというと、ひと昔前に比べて、③の主体的に学習に取り組む態度 の点数が占める割合がかなり大きくなりました。これは、学校での授業態度や提出物があたります。教科の先生にもよりますが、全体の4割~5割程度占めると思われます。これによるメリット・デメリットをまとめます。
・メリット 授業態度や提出物の割合が大きくなっている分、テストの割合が小さくなっているので成績が取りやすい。今のつけ方だと教科の先生にもよりますが、70%~80%が4、80%以上で5をもらえるような成績のつけ方になっていると思います。(ひと昔は、80%以上で4、90%以上で5でした。テストで9割切るとまず5は厳しかったです。)去年の生徒にはテスト78%で5をもらっている生徒がいました。
・デメリット 授業態度や提出物の割合が大きくなっている分、テストだけ取れても4や5を取れなくなっている。提出物の内容も重要視されている。(テスト9割以上で3がついている生徒もざらにいます。)
去年の受験生では入塾時に評定平均3.6程度だった生徒が半年で評定平均4.7まで上がった生徒もいました。努力で全然覆る範囲だと思います。
それに合わせ、沖縄県でも定期テストから単元テストに変わってきている中学校がかなり多いです。単元テストの問題も何度か拝見していますが、やはり定期テストに比べてかなり易しくなっています。中には、学校のワークをコピーでテストしていたり、平均点が8割超えや、満点の生徒が30人以上いるテストもあります。全体的にかなり点数が取りやすい状況にあります。
受験の問題についても、傾向が少し変わったとはいえ平成の入試に比べるとかなり易しいです。去年の受験生にも平成の過去問に取り組んでもらいました。模試で200点超えるような生徒でも平成の過去問は150点にも満たない状況でした。約50点程度乖離がある状況です。
全体的にまとめると、テストの占める割合が小さくなり、単元テストに変わり点数も取りやすいです。さらに受験の問題も易しくなった。時代的に県内上位校はかなり狙いやすいと思います。
全体的に勉強時間が減っている状況でこれはチャンスとも言えるかと思います。一緒に県内上位校も目指しましょう。
気になる方はお問い合わせください。
TEL 098-963-9073